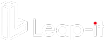社長ブログ
飲食業の求人の構造問題2
前回の続き
①重要性◯ 緊急性◯
②重要性△ 緊急性◯
③重要性◯ 緊急性△
④重要性△ 緊急性△
こういった階層があったとして、業務というのはほとんどが②までで止まっちゃうというのが構造としてあります
+①②は突発的な発生がしちゃうというのもあります
求人の構造でいえば、①②は突発的な離職が発生した場合が多い状況であり、私も多々経験しました
求人の構造を考える場合にまずはいかに①②の状況を避けるかが鍵になります
求人に対しての緊急性が発生している=現場が回らないレベルまで大いにあり得ます
その場合、先ずは「店を回すこと」が最重要課題となってしまいます(A)
そこが構造問題の根本だと考えています
さらに求人が来ない体制のままだと追い討ちをかけるように費用の問題も発生します(B)
追い討ちをかけるように、業務が複雑であったりトレーニングに時間がかかる場合の問題もあります(C)
他にもあるのですが、主にこのようなものが問題としてあげられます
(本当嫌になりますよね)
冷静になれる時にこそ、これ等の課題が発生しづらい仕組み
+対策のオペレーションを固めておく必要があります
(A)に関しては毎月各店舗のMTGにてすり合わせを行っておくことが重要です
知りたくないことに蓋をしておくのではなく、あくまで淡々と回せる仕組みが必要なので
突発的なエラーを起こらない(起こさない)ためにも入念なすり合わせが必要になります
(A-1)先ずは進捗の棚卸し(先月の振り返りとして)
・シフトが回っているか(負担が偏りすぎていたり、無理が起こっていないか)
・シフトに対する問題があったかどうか(当欠が多いor遅刻が多い等も含む)
この辺りの振り返りが必要になります
ここで重要なのは対策をする前に先ずは事実確認を優先させること
先ずは情報の抜け漏れがないように淡々と、淡々と(事実を知ることが最重要)
(A-2)その次に卒業予定のスタッフのすり合わせを共有
(最低でも3ヶ月先の状況にしておくこと)
本部のフォローとして求人を打ったとてそれが明日、明後日解決するのは運任せになってしまいます
バッファを設けておくためには3ヶ月後のマネジメントを把握しておく必要があります
この辺りの情報共有が進むだけで、店を回すことが最重要課題になる求人を打つことが避けられます
次に(B)の案件:求人の費用対効果の話です
先ずはアルバイト・社員ともどちらにせよ応募単価の把握が必要になってきます
・応募単価
・応募人数
・面接実施率
・面接実施数
・採用率
・採用人数
このように因数分解が必要となってきます
その前に予算があり、最終的には採用単価が算出可能ですが、一旦無視をしておいて
先ずは状況を把握する必要があるので
この辺りを棚卸ししておくことにより、いくらでフォローができるのかというのが見えてきます
ここを一色単にしているからこそ、本部・現場の力技になってしまっているのが構造としての根本原因です
先ずは棚卸し(実地調査)をして、費用が高すぎる場合は見直しが必要になってきます
待遇や価値訴求の見直し
理想は待遇に関しては、地域の中で頭二つくらい飛び抜けているイメージ
そもそもの応募単価が高く、費用が高いために採用率が高くなってしまっている
これが根本の原因なのです
理想は応募単価が低く、応募人数が集まる中で適正に判断し採用を行う
その結果採用率は50%や70%の高い数字ではなく、10%程度になったよね
ただ妥協の採用をしなくなったことにより、良い人材が集まっているよね
かつ予算も少なくて済んだ
あくまで費用は有象無象にかければ良いというのではないので
と、いうのが目指すべき青写真です
ここまでボリュームが多く感じると思いますが、
一度勝てる仕組みを作ってさえしまえば良いのであって
それに手を避けないままだとずっとリスクを孕んでいる状況であります
他にも細かいことはあるのですが、要約するとざっとこんな感じです
大変ですが、エラーや失敗を恐れるよりもフォローに強い体制ができることが重要です
(C)に関してもボリュームが多く細かいことがたくさんあるのですが、
それ等はNewtonで解決出来ますよ
2025/07/31