

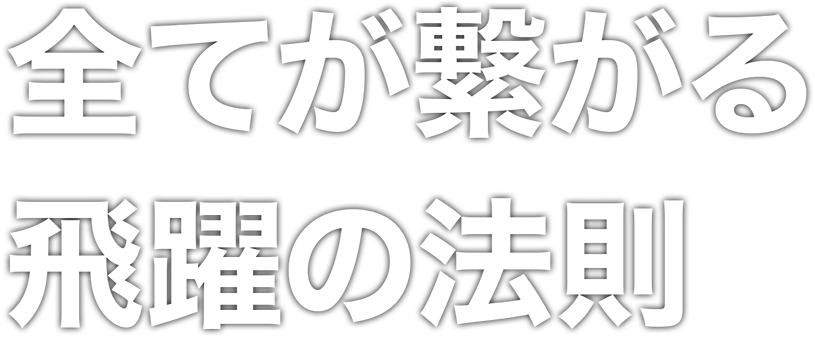

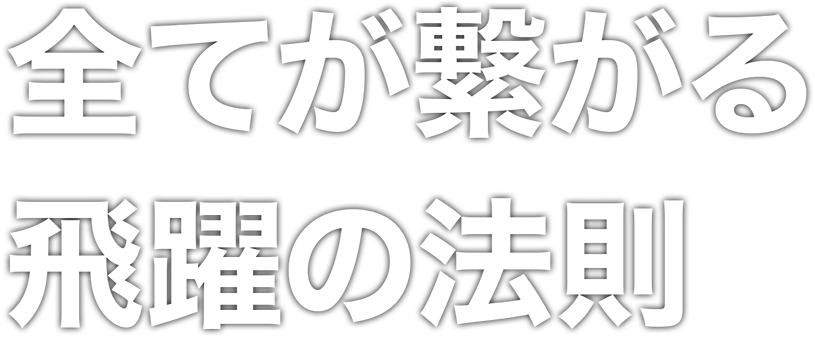
会議では前月の振り返りを行い、当月の進捗、来月の計画が上がってきたものを承認
そのような流れで進めています
まずは数字を元に判断し、分析を行います
その数字をもとに対策を立て、行動計画へと落とし込みます
もちろんやればやるほど成長するような
前月よりも今月、今月よりも来月といった感じでとんとん拍子にプラスを積み上げられていければ良いのですが、現実はちょっとした積み重ねで左右されていくような感じです
一発逆転!なんてことはなく、日々の積み重ねが重要であります
会議の中で
「あれ?まだ前回のもの終わっていないの?」
「ん?テストも進んでいないじゃん」
といった事象がポツポツと発生していました
今まではマイナスを埋めれば良いという状況でしたが、今後はプラスを作れる体制にするべくこの辺りはネジを閉め直そうと思っています
結局は行動をしたかどうかなんですよね
結果というのはその次の話
あーやこーやと出来ない理由ではなく、きちんと行動をしたかどうか
やる前にはいろんな感情が出てくるもんですが、そこで判断しちゃうと前進しないので
何より行動した後に、
「面倒だけど、やって良かったわ」と思ったことってたくさんあるはずです
大半の出来ない理由としては夏休みの宿題のように後回しにしてしまうからなんです
後になればなるほど、宿題というのは空白を埋めるゲームになってしまいますよね笑
これも経験があるはずです
そして空白が多いままで
「まっ今年の宿題は仕方ない!いっちょ怒られようか!」
といった気持ちになるはずです笑
あるあるですね笑
まぁ言い方悪いですが、飲食業に準じている大半は勉強なんて△◾️#の方が大半ですから笑
もれなく私も含めて我が社のスタッフもそうですよ笑
最近スタッフも見ているらしいので(チクっと釘をさしておきます笑)
仕事だから、お金をもらっているんだから、会社として成長させないと
色々方便はありますがそんなことで指示をするよりも一番は
「やって良かったな」と感じられることが私は重要だと感じています
私自身はそこのみで動いているといっても良いくらいです
1日の振り返りに今日もやっていて良かったなと思えるかどうか
もちろん面倒だなと思うことなんて多々ありますが、
面倒だと思うこと=重要なことだ
とも思っています
あと、宿題を埋めて終わりではなく、先に仕上げておくことにより
「あれ?なんかあそこ間違っていたんじゃない?」といった時間も作れてそれが本質だとも感じています
行動あるのみ
ですね
事業として成長するために、時に間違ったやり方のルールも存在します
会議の場で話をして「一旦やってみましょう」と決まったこと
やってみると現場の負担が大きく使い物にならない、
現場の負担が大きい場合や収益性に結びつかない場合
振り返ると全てが全て、上手くいくのではなく「あの頃は青かったね」そんなイメージ
とは言え、その場で決まったルールである以上現場は徹底をしないのは間違っています
それなら会議の場で伝えておくべきで
「何となく決まったけど、気に入らなかったらやらなければ良いか」こういった取捨選択はありません
それを許容していると次に進めないどころか、既存の業務にも変なマイルールが登場するようになります
やってみてあまりにも不具合が多いケースも然り
不具合が多いからといって「やらないでいっか」となるケースはダメです
現場の方は面倒だけども気づいた時には連絡を入れて、どうすればより良い方向に進められるかの議論ができる必要があります
「お客様」「現場」「会社」と三方の登場人物がいますが、経営ではそれらがより良くなるために考えたことで決して「会社」だけが甘い汁を吸おうというのではありません
現場の負担が大きすぎるのもダメだな、かといって現状と同じでもダメだし
事業である以上は常に進化ができるようにしないとダメで、今まで通りだとどこかで通用しなくなるケースも多々あります
とは言え、新しいことは新店をオープンすることと同じような感覚で何もかも全て狙い通りということは多くありません
色々とパターンを作っておき、良いところをさらに伸ばしていく
そんなイメージです
先ずはテストでやってみて、さらにより良くなるテストデータを集めてさらに投資をするかどうかの判断をしていく流れです
決して、気分で決めたわけではなく、それ相応の思いがあるということです
上手くいったら成功パターンが増えてこれは会社・現場ともに大きな資産となります
その途上ではすぐに上手くいくパターンなんて少なく、実際は回しながらブラッシュアップを繰り返して安定性を増していくためには双方の協力が必要になってくるわけで
実際にやってみて、さらにより良くするためにはどうすれば出来るか
できない理由ではなく、どうすればより良くなるか
これらがチームとして重要になってきます
「計画」は兎にも角にも重要と感じています
経営者の仕事として重要なのは事業計画であり、ここに妥協はしたらダメであります
計画こそスタッフや関連企業を変える最大の効果があるので
私自身計画作りの重要性を身をもって体感しています
出店をするためには取引先や銀行の協力も必要になってきます
もちろんスタッフの協力も必要です
スタッフ自身にも計画を作る習慣を身につけてもらえるようになると良いチームが出来上がります
計画を見るとある程度の考えも分かってきますし特徴も見えてきます
強気すぎるや弱気すぎる
さらにそれらを達成するための行動ベースで因数分解まで落とし込めている
よく見えている場合やここは甘く感じるな
もっというと日々◯か×かでチェックできるようになっているか
チームでの話となると計画を責任者が立案・提案し、上司が承認をする
ダメだったら修正を依頼するという形をとるだけで大きく変貌しますよ
「時間がないから」と言って妥協してしまうのは非常に勿体ないです
具体的な作り方として
「売上は少なく」「支出は最大化」がオススメです
売上には過剰に期待せずにシビアにストレスをかけておく
支出は余裕を持たせておく
それで利益が出ているかどうか、出ていないなら修正を繰り返す
ただ、前提としては売上は少なく、支出は最大化
でないと、余裕のない状況で回してしまうということになってしまい、それだと精神衛生的に良くないですので
数字を読めるではなく、数字を作れるところまで持って行きたいですよね
改めて振り返ってみると、飲食事業ではそれこそ年間計画は過去のデータやフォーマットがあるので
作成:2時間
▷修正:2時間
▷修正:2時間
で出来ます
会計事務所の方と作るのですが、毎月のすり合わせを行っているのでサクッとできます
システム事業に関しては純粋な稼働日数でいうと3週間ほどまるまるかかりました
フォーマット・前例がないと大変なので専門家にも依頼をしてこれなのでだいぶ掛かりますね
飲食に関していえば、計画に対して実績はポジティブな結果なので銀行担当者はびっくりしていました笑
もちろん驚かして終わりではなく、信頼関係が形成されるのでその後の動きもだいぶスムーズに運べます
兎にも角にも計画ですね
ここで勝てる戦略を立てられるかが重要です
人の行動を評価するときに単なるオペレーションだけを評価すると行き詰まってしまいます
「この人は仕事はできるけど、チームとしてはうまく機能していない」
「ある程度までは任せられるけど、深いところは難しいんだよなぁ」
よくある例として、こんな壁にぶち当たってしまいます
行動の評価とは、もっと因数分解をして判断をすることが非常に重要となります
①スタンス
②スキル
③マネジメント
チームとしての信頼関係を構築する際にはこの指標があると非常に便利です
さらに優先順位としては、
①>②>③ですね
ちなみにですが、生産性(売上up・支出down)に関しては逆の順になります
③>②>①
その為に会社独自で作成している評価制度は、重要なところが届きづらい制度になってしまいます
それでも回らなくはないのですが、チーム形成に関しては短距離走ではなく長距離なので生産性も加味しつつ、チームの透明度を上げると行ったことが大切です
もっというと覚える順番も①>②>③の順番ですね
スタンスは癖がついちゃうと変えるのはなかなか難しいですよ
具体的なことと言えば、
・挨拶ができる
・掃除ができる
・時間を守る
こう言った当たり前の基準なのですが、ここの部分を後回ししちゃうとその後のチーム形成に関して正直ものがバカを見る状況のリスクが生まれやすくなります
個人として働く場合なら問題ないのですが
(それでもクリエイティブな部分では突っかかりますが)
チームとしての場合だと淡々と評価して判断するのが一手目としては必要です