

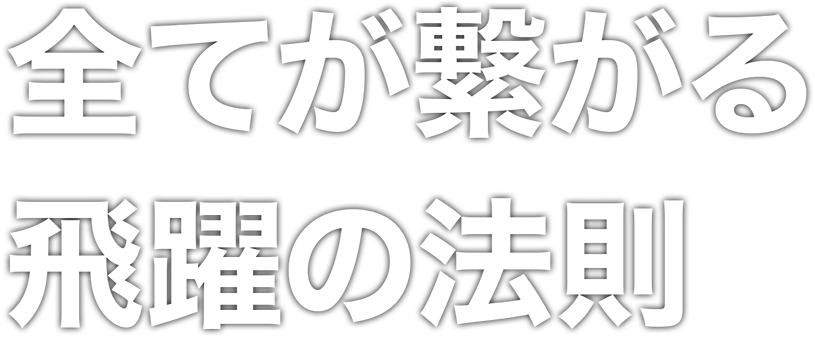

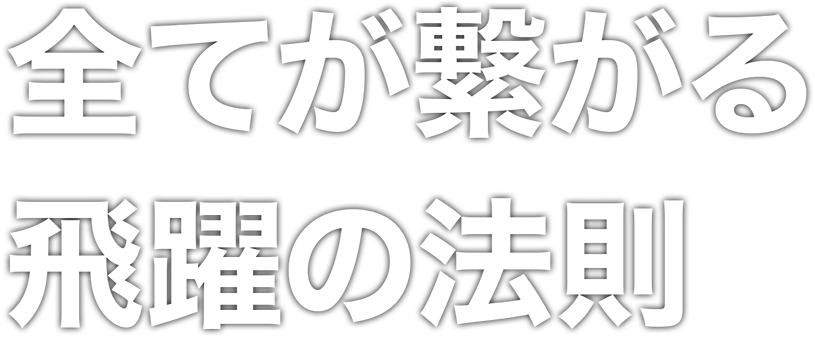
タイトルにある通り「5人の平均値が自分の実力」と言われています
5人の条件とは自分にとって関わりの深い人っていうことです
社会人や学生の状況によって変わってきますが、友達や同僚がほとんどだと思います
その思い浮かぶ5人の平均値が自分の実力です
2通りの考え方があって
・自分自身のこと
・チーム運営のこと
この2軸で考えることができます
一般的な方は自分自身のことだけでは良いと思いますが、
経営層・店長等の責任がある立場の方はチーム運営の視点でも
フィルターとしてあった方が良いですね
チーム運営のことで言えば「スタンス」が特に重要ですが、社内文化の形成がこれらに当てはまります
よく説明の場ではチーム作りは、稲作と一緒だと伝えています
稲作で言えば、
土を耕し、種を植え、水やり草抜きをし、収穫といったサイクル
これをチーム作りに置き換えると、
土=>ルールや仕組み
種=>人
水やり・草抜き=>注意や誉める(教育)
収穫=>文字通り生産性UP
このサイクルでやるのが非常に重要で種=人に求めすぎても限界がありますし、そもそも土を作り直す必要があるかも知れません
例えば、新しいスタッフが入った時に
・遅刻が頻発している店舗
・清掃が疎かになっている店舗
こういうのがスルーされている状況だったら自ずと癖がつきやすくなるのと一緒で
平均値を上げる仕組みを作ってから人に求めると生産性が上がりやすくなります
人の行動を評価するときに単なるオペレーションだけを評価すると行き詰まってしまいます
「この人は仕事はできるけど、チームとしてはうまく機能していない」
「ある程度までは任せられるけど、深いところは難しいんだよなぁ」
よくある例として、こんな壁にぶち当たってしまいます
行動の評価とは、もっと因数分解をして判断をすることが非常に重要となります
①スタンス
②スキル
③マネジメント
チームとしての信頼関係を構築する際にはこの指標があると非常に便利です
さらに優先順位としては、
①>②>③ですね
ちなみにですが、生産性(売上up・支出down)に関しては逆の順になります
③>②>①
その為に会社独自で作成している評価制度は、重要なところが届きづらい制度になってしまいます
それでも回らなくはないのですが、チーム形成に関しては短距離走ではなく長距離なので生産性も加味しつつ、チームの透明度を上げると行ったことが大切です
もっというと覚える順番も①>②>③の順番ですね
スタンスは癖がついちゃうと変えるのはなかなか難しいですよ
具体的なことと言えば、
・挨拶ができる
・掃除ができる
・時間を守る
こう言った当たり前の基準なのですが、ここの部分を後回ししちゃうとその後のチーム形成に関して正直ものがバカを見る状況のリスクが生まれやすくなります
個人として働く場合なら問題ないのですが
(それでもクリエイティブな部分では突っかかりますが)
チームとしての場合だと淡々と評価して判断するのが一手目としては必要です
仕事には「丸投げ」ではなく「任せる」という事が必要になります
これにもきちんと仕組みを構築しておかなければなりません
仕組みを理解せずに正しく振れていないと、
・仕事を振ってみた後に返ってきた答えが違う
・思った以上に時間がかかりすぎている
と言ったエラーの発生が多くなってしまいます
「これぐらい分かってよ」
「細かく説明しなくても考えてくれれば分かる事なのに」
「なんで手が止まった時に聞いてくれないの」
これらが経営者や上司としての立場の方が思う事ですが、
価値観のギャップに感情的なものは一切省きこれからの時代は、合わせていかねばなりません
特に、ますますギャップは広がっていくと思いますよ
業者さんに関しても然りで、例えば非常にまずい例の場合、
新規出店時の設備は間違えられてしまうと大変なことになってしまいます
あくまで専門家なので、素人のような失敗はないにしろ
・厨房内の冷蔵庫や作業場の配置が悪く導線が悪い
・吸気と換気のバランスが悪い
的な微妙な部分などが挙げられます
本来はこちらも気づくべきなのですが、
業者さんの質によってはそれ以前の指摘が多すぎてその辺りまで辿り着けないケースも然り
もちろん対応はしてくれるのですが、ひどいところだとそれすら追加料金が発生の恐れも
本音としては
「えっ、プロでしょ?設計の段階で気づかなかった?」
「作業取り掛かる前に指摘や指示が欲しかったんですけど」
と言うのがあります
なので任せ方としては
・人を変える=プロに任せる(スタッフ・業者さんを変える)
・任せ方を変える
この2パターンですね
もちろんそれぞれにメリット・デメリットがあり
前者だと費用、後者だと時間が大きく掛かる要因です
あとは余力との話になりますが大体は後者のパターンになってくると思います
なので任せ方自体を変えないといけないですね
具体的に
・任せる前に青写真をアウトプット(動画>写真・イラスト>文字)
・作業前に説明・すり合わせ
・期限の確認(アナウンス方法)
出店のようなイベントならモチベーションが上がってなんとか我慢ができるのですが
(それもある一定店舗数までは)
普段の指示については省きたくもなりますね
なので普段のルーティン業務は、
タスクを棚卸ししておくとズレが起こりにくくなり双方が納得しやすい環境が作れます
そこに目を背けて蔑ろにしておくとバケツの穴が空いてる状況になってしまいます
そこは経営者や責任者がしないといけない仕事です
ただその上流の作業って非常にデリケートで
どこから手をつけて良いのか分からないのが本音でもありますね
業務チェックレベルならともかく
(と言ってもそこにもエッセンスが膨大に詰まっています)
我々としては設計に自信をもってやっております
「仕組みを作る」と言うことは
「社内文化を変える」と言うことでもあり
大変な責務であります
外部と言った気持ちではなく、
プロとして上流の部分の伴走しっかりとさせてもらいますよ
もっと言うと親戚の甥や姪としての意気込みで取り掛かっているのでその辺りは違いますよ
ありがたいことに商談の回数が増えており、最近は同席もさせていただいております
みなさん後者(任せ方を変える)に対して取り掛かろうとする意欲がもの凄く伝わりますね
自画自賛ですがシステムとしてもなかなかではなく、かな〜り良いです
先日は私含め営業チームが、日中トイレに行く時間もないほどでした笑
多分どこかで大バズりするのですが、
本音ではまだこの熟成期間のような今を楽しみたいです
私自身、飲食店経営者として10年以上やっておりますが、
就寝時間は21:00です笑
起きるのは4:00ですが
毎回この話をするたびに驚かれたり、
もしくは「この人、人生に楽しみあるの?」的なイメージで見られたり笑
外に視察がてら出かける時や臨店の時は、
もちろん夜中までありますが基本的に朝方人間で
それが性分に合っているんですよね
日課としては朝日報を見てから1日が始まるといった感じです
何か気になることがあれば返信をしてといった感じ
昔は週に2回ほどやっていたのですが、それらもどんどん減らして今はこの形です
最近はその返信業務も任せられるようになってきたのでどんどんシステムに注力が出来ています
基本的に店舗のミーティングも月に1回のみだし
それも基本はオンラインでやっており、臨店にする機会も減ってきています
よく
「社内での人間関係が希薄にならないですか?」
「それでどうやって店を回しているんですか?」
「問題って起きないんですか?」
と言ったことを聞かれるのですが、絶好調ですよ笑
去年から私自身が東京に来ており、
離れている体制がメインではありますが
過去最高売上・利益を更新していますし
もちろんスタッフには感謝しております
稲作の考えを仕組みづくりに取り入れています
まずは土作り、次に種を植え、水やり草抜きをし、収穫
このサイクルです
①ルールや仕組みと言った良い土壌があるか
②人という種
③良いよと誉めたり、ダメなところは正しく注意して
④収穫をしましょうよ
教育のサイクルの落とし込むとこういうことです
あくまで種(人)にばかり求めすぎず、まずは土壌作りが重要ってことです
つまりルールや仕組みが重要ってことです
その点にかけては長けている自信があります
なんせ朝から何年も取り掛かっていますから笑
かと言って丸投げにしすぎても良くなく、あくまで
・承認を事前にしている
・スタッフには「共有」をし、「納得」してもらい「行動」してもらう
・指示は口頭ではなく、文字やイメージを共有
・議事録をつけ、必ず振り返りから行う
といった具体定なエッセンス(飲食っぽくいうと秘伝のタレ)があるのですが笑
それぞれボリュームが多いテーマなのでまた書き記します
全然違う話ですが、
GW中業者さんとニュートンのホームページリニューアルの打ち合わせを
毎日朝・夕みっちりやってアップデートしましたがこれは良い!
改めて自社のサービスをマジマジと見たのですが、これ凄いですね笑
それも近々アップされます(本当は本日予定)
チェーン展開をしている・目指している場合だと、役職設計をする際に
「店長のランクを設けておく」ということ
こちらをオススメしています
細かく分けると料理長・副店長も分けたいというところもあるのですが
その辺りに関しては管理体制とのトレードオフになります
とは言え、店長に関しては分けておくことをオススメしております
「店長」という一括りで管理をしてしまうと、さまざまな障害に行き当たりやすくなります
・配置転換を依頼したいけど本来の目的が伝わりづらい
・店長自身の納得度につながりずらい
主にこの2点が目的としてあります
同一業態をチェーン展開をしている場合でも、
全ての店舗が満遍なく利益率が良いというケースはなかなかないと思います
そこを因数分解して現在の状況を整理しておくのが必要です
事例として多いのはS・A・Bと3段階に分けます
それと本部の業態開発力・立地等によりそれらの概念が変わってきます
イメージが分かりづらい場合は銀行の担当者に聞いてみると大体ランクが分けられているので
イメージがしやすいと思います
売上やFL管理の属人性が高い状況であるならば
・Sランク(収益性が高い・ここを理想として展開していきたい)
・Aランク(良い感じではあるがSよりは目立たない)
・Bランク(課題が残っている)
これとは逆に、
本部の業態力・立地が強い場合はランクの意味合いも変えるケースもあります
この辺りは設計時のヒアリングによって判断していきます
この仕組みルールがあるだけで配置転換がしやすくなります
理想だけをいうと店長に関しては、1店舗だけの移動なしが良いように感じるのです
但しその理想に甘んじるのではなくどういう経営状況になっても
対応できる想定を作っておいて損はないということです
予期せぬ状況が発生した時に、対応力が強いかどうかは今まで以上に重要になってきます
仕組みがないが故に同じ痛みを味わうのも、良い気分ではないですし
仕組みとして作っておくことにより
会社・店長双方が余計な感情を省き淡々と実行できるようにするのが狙いです
業務の効率化
前回書いたのですが、業務の効率化の狙いってまずは失点を防ぐことだと思います
スポーツで例えるなら
「5対4で今までは勝っているのを5対3にしたいよね」
そんな感じだと思います
得失点差が1だったのを2にしたいよねってこと
会社経営でいうところの利益が得失点差に当てはまります
スコアが1点あたり100万だとしたら
100万の利益を200万にしたいよねってこと
(変な賭博の話ではありませんよ、あくまでイメージ笑)
効率化の狙いとしてはそんな感じだと思うのですが、
重要なのは入り口よりも出口であります
うまく施策が当たった時に、利益が増えた時に、
どうするかってことを考えておく必要があります
あくまで効率化というのは手段であって目的ではありません
例えば
・従業員に還元してさらに頑張ってもらう
・経営者が堂々と頂く(これももちろんあり)
・とにかく会社を筋肉質体制にしておきたい
・(コロナで)会社の傷んだ財務を立て直す
・お客様に還元し、さらに得点を増やす
(これは単なる6対3ではなく、少しややこしい)
他にもありますが、ざくっと上記のようなものに還元が多いと思います
これらが目的としてその後に、どう正のスパイライルが出来上がるか
とても重要な経営判断として必要になります
失点を増やすことはなんとなく重要だと感じている場合も多いと思いますが、
セオリーとして
「バケツで水を汲む前に、バケツの穴を埋める」
このことを理解しておくと納得度が増すと思います
目的としては得失点さを増やしたい(もちろんプラスで)
そのためには得点を増やすのではなく、失点を減らすこと
物事には人やお金といったリソースが限られています
どこに集中すべきかの決断の時に間違ってしまうと手痛い失敗をしたくありません
策がない状況の中選択を迫られている状況の場合
「とにかく得点を増やしたい」と焦る気持ちもあるのですが、
一旦バケツの穴を埋めることに集中して良いでしょう
かといってやりすぎも良くないのでほどほど感が重要ではありますが
経費削減だけしておけば良いというのではなく順番が大事ってことですね
効率化に関してのまず第一歩は可視化だと思っています
とにかくアウトプットをすること
これに尽きます
でないと、集まりが変な方向に行きがちになりやすいので
+議事録をつける
+議事録を必ず振り返る
こういった当たり前の建付が必要になってきます
急がば回れってことですね
また追々、アウトプットの具体例等を示していければと思います