

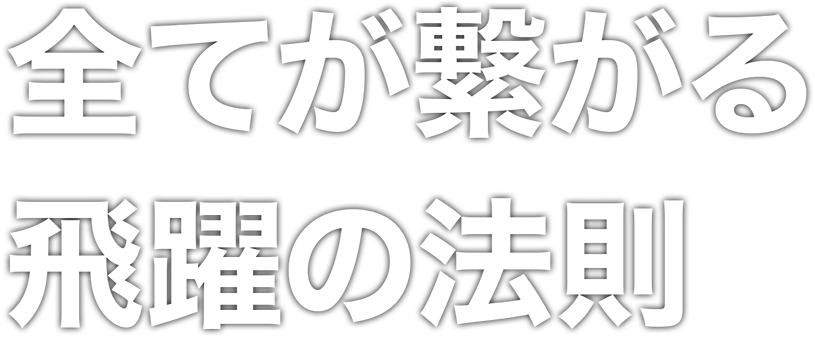

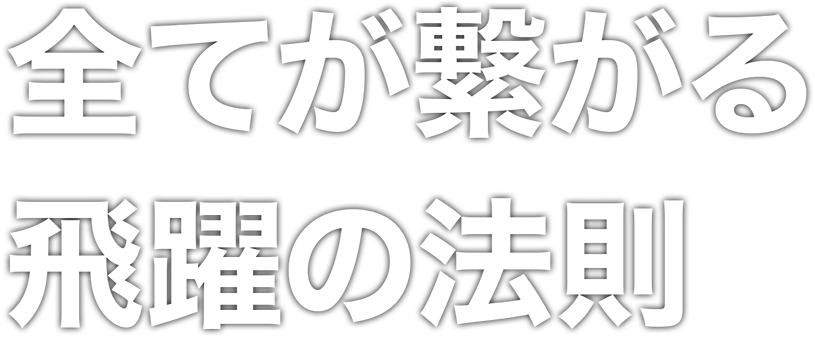
毎月一週目もしくは二週目は会議期間です
弊社の飲食もエリアごとでみっちり会議をしております
私自身、自社とは他に100店舗を運営している会社のコンサルもしており、
その会議も同じ週に重なっているためなかなかに頭を使う期間であります
その分、頭も良い感じに温まっているとも言えます
振り返りというのはもちろん早ければ早い方が良いわけです
すでに進行月が始まっているわけで、月次の振り返り事態が遅いと打ち手も必然的に遅くなります
会議資料を作るのは大変なのは分かるのですが、いかに簡略化することも重要ですね
そのためにda vinciという経営管理ツールがお役立ちできればと思います
そもそも根本の原因はあっちこっちのシステムを繋ぎ合わせないといけないのが原因であり、
私自身も非常に悩まされました
「このままではまずい」と肌感では分かっているものの、
現場スタッフが納得するための言語化まで落とし込もうとした際に、
根拠となる数字が「だろう」では悶々として結局改善されにくいというのも体験しましたし
いかに早く情報をキャッチアップし、ボトルネックを見つけブラッシュアップが必要となります
なので重要なのは改善ができるための情報の質を確保しつつ誰もが共有できる仕組みが先ずは必要となります
店舗運営において、今が良かったとしても一概に良いとは言い切れません
再現性があるかと言えばそうではありませんし、
スタッフが入れ替わると崩れてしまうことというのも避けられるようにしなければなりません
属人性からの脱却が必要であり、スタッフを辞めさせることを推奨しているわけではないですよ
学生アルバイト主体の場合だと、もうそろそろ入れ替わりの時期が必然的に来ますし(もちろん残ってくることに関しては万々歳ですが)その時を見据えて余裕を持っておこうという話です
余裕がないと送り出す時も仕事に追われている状況ですが、
余裕がある場合は「またいつでも食べにおいで」とスマートな会話ができるように
その安定性を強化するためには月次の振り返りはもちろん、日々の振り返りも重要となってきます
経営会議においては自店の強みを磨き上げ、
お客様に更に支持をしてもらえるような仕組みづくりが必要となるわけです
ネクストアクションとタイトルにありますが、会議期間を振り返り思ったことはやはり行動計画が重要だということです
先月の振り返りを行い、
「ここはもっと伸ばせるから更に継続して伸ばしていく」
「ここは正直もうちょっと頑張れたので当月は引き締めていく」
ざくっとこんな感じですね
但し、
重要なのはその行動指標が店舗の生産性UPに本当に繋がっているのか?
優先順位は本当に合っているのか?
例えばFLはOKで売上がまだ伸ばせる場合
この店舗の場合は原価コントロールやシフトの調整はクリアしている
そうなった場合に売上だけにフォーカスをして行動計画を立てるのが良いですね
客数なのか(さらに新規orリピーターor来店頻度)
客単価なのか(注文数増加or単価up)
これらが先月の振り返りと一気通貫となっていないと意味がありません
逆にこれ等が一気通貫で見えている人は結果が面白いほどに出てきます
「あっ見えているんだな」というのが伝わってくると
必然的に行動も大丈夫なんだなと思える、そんな感覚です
うーん、頭が温まっているために、伝えたいことはたくさんあるのですが、
会議というのは生モノなので言語化するのが難しいですね笑
私のネクストアクションは伝わりやすい言語化を強化するために、ブログを書きまくることですね笑
人事評価システムがNewtonであり、管理会計システムがda vinciとあります
da vinciは現在テスト中で、良い感じで進んでおります
近々一般公開が出来そうで、良いシステムとして完成しそうです
(自社ではテストで数年試していますが)
このようにどんどんアップデートをしております
まだまだしたいことがたくさんあり、大変ですが笑
全ては単純にシステムに移行したいという思いではなく、商売としてはあくまで生産性を良くする
その言葉に尽きます
私自身が飲食店を経営しており、課題を抽出しアップデートしていく必要を感じていますので
経営の状況というのは年々難しくなってきています
人口の減少が大きな要因と言えますが、他には物価高や情報の広がり方等
選択を間違えてしまうと、とんでもないことになりかねますし
選択をするためには正しい情報が必要であり、精度を上げる必要があります
何故システムを作ったのか?システム事業に参入したのか?
これは全て経営を通じて実践をしたからこその賜物です
私がよく業者さんに言うのが「真剣」と「木刀」と「竹刀」の違いと言っています
痛みと覚悟の話ですね
気の利いた話をする業者さんもいますが、それって「木刀」レベルの思考だよねと思うことがあります
経営者である私としてはその話を試してみると、腕がなくなっちゃうリスクもあるよねと思うようなことが多々あります
あくまでイメージの話です笑
私自身もそうですし、他の経営者の方ももちろんそうですが、痛みなんて味わいたくないですよ
ただ前進するためには痛みがつきもので
そのリスクをいかに減らすかは活きた情報が大切になってきます
da vinciは良い感じで着手しており、これは実際に手応えを感じております
Newtonに関しては、今後OPEN、CLOSEチェックリストも導入できそうです
なぜ作ったかと言えば自社での課題があったからですよ笑
正しい業務を行える環境作り、情報が上がってくる仕組みは重要ってことですね
人事評価Newtonというのはあくまで会社にとってのツールであります
評価制度というのは「ヒト」「モノ」「カネ」の「ヒト」「カネ」の部分に携わり非常にデリケートな扱いであります
思いつきでやってしまうと現場が混乱するだけですし、経営とマッチしているかも考える必要があります
それに現場の生産性を連携したり、スタッフの体制を考えたり
それらを抱え込んでしまうとどうしても後回しになってしまい悪循環になってしまうケースがあるもののどこから手をつけて良いのか分からない
正しいものと言える自信が持てない
そういうのを払拭して会社さんのアップデートに役立てるように努めています
・会社として曖昧だった評価制度を設計する上でのオンボーディング
・評価制度の項目を一から作るのは非常に手間が掛かるのでテンプレートをベースにて添削
・設計後、スタッフさんに対して、
単に業務が増えたと思われるのではなく評価制度の立ち位置を理解してもらえるようにサポート
我々は単にツール売りではなく、その後の成長に役立てることを非常に重要としています
導入という入口だけに捉われず、その後の成長を重要視しています
おかげさまで評価制度の精度やサポートに関しても高評価を頂いています
「なるほど、こうやれば良かったんですね」
「これだったらスタッフのモチベーションも維持できますね」
もちろん評価制度の仕組みを覚えてもらえるなと感じられた時も嬉しい瞬間であります
店舗ビジネス、人が主役な商売として細かく考えられていますし笑
実績もありますね
アップデートしてもらえたなと感じる時も嬉しいのですが、それよりも嬉しいのはシステムを会社で回せる体制になっていっていること
これが私として非常に嬉しく感じる事柄であります
あくまでNewtonはツールとして、会社としてどんどんブラッシュアップができる
それらの手助けができるのを感じられると「あー作って良かった」と思えるんですよね
評価制度は仕組みを構築するのが大変なんですが、まずは骨子を作ってブラッシュアップが必要となってきますので
メニューブックのように作って終わりではなくどんどんアップデートが必要となってきます
私自身も自社のメニューブックをアップデートしますが、
その時って特に前向きというか宿題をやらなくちゃくらいの意識でやっています笑
「本当はそんなことしたくない」というのが大本音です笑
理想を言うなら作りっぱなしが良いよねって思っていますし
但し、経営をしている上で成長を考えた時停滞はダメだからやっているのであって
その時って手間も多いし
(写真を撮り直し・それに携わる準備・値入れ・原価再確認・皿の準備)
仕組みが後手後手だと本当当面はとしたくないと思ってしまいます笑
評価制度の場合も同じで、手間が少なくアップデートできるようにNewtonを設計したので
「これ効率めちゃくちゃ良いですね」そう言われると嬉しいポイントです
どんどん設計のキッカケを機に社内が活性化しているのを見ると嬉しくなりますね
スタッフに業務を振ってみて任せてみる
任せていた業務が期待していた答えでない結果になること
と、いうのは残念ながら発生していしまいます
【通常業務】で発生している場合
【新しい取り組み】で発生している場合
二通りに分けることができるのですが、前者の場合であれば社内での共有の方法を変えないとダメです
業務を棚卸ししてみて、
どこに問題が発生しているか、
発生しやすいか
人によって迷いやすい場合等、特徴を抽出して対策を立てていきます
逆に後者の場合
通常業務は優秀なスタッフだけども、新しい取り組みに関しては任せると不安が残るような場合
今まで任せてみて全然思っていたのと違う
こういうケースは多々あると思います
一見価値観が共有されているように感じるのでこの新しい仕事も任せてみるのですが、
却ってきた結果が期待しているのとはちょっと違うよなといったケース
・指示の仕方が曖昧
・ゴールの解釈ができていない
色々と原因はあるのですが、指示を細かくはしたくないものですものね笑
「そこまで噛み砕いて言わないといけないの?」という気持ちになりますし、
「これくらいはできるでしょ」という思いもありますし
問題の大半として、ゴールの姿のすり合わせが行えていないことにあると思います
指示をしてみて相手が理解しているように感じるのですが、
いきなり任せるのではなく事前にヒアリングをしてみるとズレが防げるケースがあります
「◯の場合、△の場合、×の場合を想定してみて聞かせて」
こんな感じで
事が起こる前にフィードバックをもらうことで
「あっそういうふうに解釈していたの?」というすり合わせが行え、
これが非常に大きい効果を発揮します
「◯は共有できているんだけども、△・×のパターンがそもそも違う」
「△が限りなく出そうだけどもその場合対策も事前に必要だよね」
といった感じですり合わせを事前に行えることによりズレを防げます
大半の業務は瞬間で解決したり2,3日で解決するものがほとんどですが、
これが1ヶ月単位の仕事だと損失が大きいケースだって発生してしまいます
チームとして気持ちよく進めるためにはスタッフ自身に自立・自走してもらえる環境が必要で
そのためにはスタッフ自身が「考える習慣」を作ってもらい、
アウトプットをする癖・それを元に事前すり合わせが行える環境を構築できると生産性が良くなります
大半は△・×がないパターンが多いのでそこはじっくりとすり合わせをしていきましょう
価値観がぐっと合ってくると精神衛生上も結果も良くなってきます
久々のブログになります笑
振り返れば直近の更新が約3ヶ月前
その間スタッフを増員したり、インフラを整え直したりと社内のレベルアップに集中していました
我々はプロとして更に顧客に納得してもらいやすいように整理作業をどんどんブラッシュアップ
おかげさまで問い合わせも多く、改めて人の課題や給与設計の課題の重要性を感じております
チームの規模が大きくなってきたのもあり改めてブログにて代表である私の考えを伝えないとと思い、
書き記していければと思います
方向性を伝えるのは重要ですのでね
最近の評価制度設計に携わりながら思うこと
まず、やはり多くの課題としてあるのが「スタンス」の重要性
人の良し悪しに対して「スタンス」「スキル」「マネジメント」の3段階に分けて分析すると見えてきます
「スタンス」とは姿勢の部分で、
具体的にいうと挨拶ができるや時間を守ることができると言った当たり前の項目
ここに課題を抱えられている方が多く感じます
「スタンス」に関しては、癖のようなもので
それって若いうちに伸ばすのが得策です
あとは入社したての段階で(鉄は熱いうちに)
どうしても人によっては直りづらい部分があるので口酸っぱく言い続けるか、それとも淡々と評価にしていくのか
対策としては給与と結びつける「具体的に言えばそのスタンスだと査定に影響しちゃうよ」にするのが初手の対策になります
時間や挨拶は本当単純に変えられないと後々大きなエラーが発生しやすいので特に気をつけないとまずいですね
周りの影響もありますので
もう一つ取り入れた方が良いと思うのが共通言語を作っていくということ
具体的にいうと「報告ごとは一方ではなく三方での視点で」
というだけで大きく変わってきます
箱物ビジネスとして単純に考えると
「お客様」「現場」「お店(会社)」
の三つの視点で報告をもらえるようになるだけで話の質やコミュニケーションの質が向上されます
例えば飲食店の場合、
管理職の方(オーナーやSV、MG)が現場責任者(店長)から
「冷蔵庫の扉が壊れました!修理してください」
と報告があったとします
これは「現場」だけの目線です
管理職の方からしたら「えー、費用かかっちゃうけど仕方ないよね」とはなりますが
「この間、臨店で見に行ったとき外国映画ばりで扉閉めていたよな」
というのが引っ掛かるケースもあります笑
再発防止を促すのも重要なのでそこを指摘すると
「じゃあお客さんには傷んだもの提供して良いんですかー?」と極論的な話になってしまったり
「現場のスタッフがこれじゃあかわいそうですよ」とやたら変な方向に話が広がるケースにまでなってしまう可能性があります
極端な例ですけどね笑
まぁ現場の方はその場で物事を目の当たりとして見ているのでどうしても熱が入りやすくなってしまうのも分からなくもないのですが、感情論での議論を如何に避けてるのが重要ですね
今後の対策に対してお互い気持ちよく進められれてより安定的な経営に繋げられるのが目的であります
なので先ほどのケースであれば先に三方の視点にて報告をもらう癖をつけることで感情論のやり取りは防げ、再発防止も現場からの提案がしやすくなります
先に本社としてフォーマットを用意しておいてあげても良いですし今の時代ならコミュニケーションツールでのやり取りもあるのでテンプレートを用意でも良いですね
大衆焼肉A店:冷蔵庫の扉故障に関して
(お客様)
今回故障したのが調味料を保管のところなので直接的な問題はないが冷蔵庫の故障になりそうなので修理をお願いたいです
(現場)
忙しいときにはスタッフの扉の閉め方が乱暴に感じる時があるためそこは再発防止として注意をしていきます
(会社)
A社・B社に見積もりを取ったのですがB社の方が5,000円ほど安くアフターサービスもしてくるとのことなのでこちらに依頼したいです
ざくっとこんな感じで、内容の質は一旦おいておいて三つの視点をあらかじめ報告もらえるだけで全然2,3手目の動きが変わってきます
この場合だと会社としての備品に対する取り扱い注意の情報も溜まってきますしね
重要なのは最初の段階でエラーが発生しづらい仕組みづくりをすることです
仕事をしている上で重要なのがカテゴリーです
飲食の事例で言うと、いかに各カテゴリーごとに注文をされるのかが重要になってきます
例えば1〜9までの各カテゴリーがあり、その下に商品群があるといった感じで
それらを基に分析をすると経営の判断がしやすくなります
例として焼肉業態をあげると
1には野菜
2には生もの
3にはタン
4にはハラミ
5には赤身
6にはホルモン
7にスープ
8に米・〆
9にデザート
これら9カテゴリーの下に商品群があるといったイメージです
(※なぜ3と4をあえて分けているかは考察してください笑)
まずはカテゴリーの定義を決めて、商品を当てはめること
改善の一丁目一番地として非常に重要になってきます
ここを理解していない専門家がやってしまうと後々の手間が増えてしまいます
カテゴリーにて分析を行うことは非常に重要なものが見えてきます
1〜9まで満遍なく頼んでもらうのを仮に良い注文方法だと定義した場合、
どのカテゴリーをもっと伸ばすのかが判断しやすくなります
セオリーとしては
・売れている商品をもっと売る、の方が結果が出やすいです
・売れていない商品力のUP
こちらも重要ですが、まずは分析を行える体制があること
もちろん全て頑張らないといけないのは分かりますが、あえて減らすことも重要です
「8の〆まで食べてもらうことにお客さんの満足度が測れるんじゃない?一旦試しみないか」
といったような会話
こちらが非常に重要になってきます
どれくらい重要かと言いますと、チームとしての会話がカチッとはまってきます
先ほどの例でいえばカテゴリーは1〜9と9種類あります
その下に商品が10ずつあれば、総数としては90あります
シンプルな会話をしつつ生産性を向上させるためには90種類の会話をするよりも9種類の会話をする方が断然結果が出やすいです
スタッフも迷いがなくなりますしね
よくあるケースとして、
「このスタッフめっちゃ頑張っているのに結果が出ないなぁ」
「仕事を任せたのに返ってきたのが違う」
といった場合は90の方を頑張っているケースが多いです
大所高所が見えていないというかすり合わせが行えていないケースに陥っているってことですね
このカテゴリーの重要性は色んなところで役立ちますよ
商品分析だけではなく、教育指標のマニュアル
仕事の振り方・任せ方
様々なメリットがあります
せっかく時間を費やしてもらうなら、結果を求めてしまいますよね
その場合はカテゴリーで判断をすることで生産性が上がりますよ
タイトルにある通り「5人の平均値が自分の実力」と言われています
5人の条件とは自分にとって関わりの深い人っていうことです
社会人や学生の状況によって変わってきますが、友達や同僚がほとんどだと思います
その思い浮かぶ5人の平均値が自分の実力です
2通りの考え方があって
・自分自身のこと
・チーム運営のこと
この2軸で考えることができます
一般的な方は自分自身のことだけでは良いと思いますが、
経営層・店長等の責任がある立場の方はチーム運営の視点でも
フィルターとしてあった方が良いですね
チーム運営のことで言えば「スタンス」が特に重要ですが、社内文化の形成がこれらに当てはまります
よく説明の場ではチーム作りは、稲作と一緒だと伝えています
稲作で言えば、
土を耕し、種を植え、水やり草抜きをし、収穫といったサイクル
これをチーム作りに置き換えると、
土=>ルールや仕組み
種=>人
水やり・草抜き=>注意や誉める(教育)
収穫=>文字通り生産性UP
このサイクルでやるのが非常に重要で種=人に求めすぎても限界がありますし、そもそも土を作り直す必要があるかも知れません
例えば、新しいスタッフが入った時に
・遅刻が頻発している店舗
・清掃が疎かになっている店舗
こういうのがスルーされている状況だったら自ずと癖がつきやすくなるのと一緒で
平均値を上げる仕組みを作ってから人に求めると生産性が上がりやすくなります
人の行動を評価するときに単なるオペレーションだけを評価すると行き詰まってしまいます
「この人は仕事はできるけど、チームとしてはうまく機能していない」
「ある程度までは任せられるけど、深いところは難しいんだよなぁ」
よくある例として、こんな壁にぶち当たってしまいます
行動の評価とは、もっと因数分解をして判断をすることが非常に重要となります
①スタンス
②スキル
③マネジメント
チームとしての信頼関係を構築する際にはこの指標があると非常に便利です
さらに優先順位としては、
①>②>③ですね
ちなみにですが、生産性(売上up・支出down)に関しては逆の順になります
③>②>①
その為に会社独自で作成している評価制度は、重要なところが届きづらい制度になってしまいます
それでも回らなくはないのですが、チーム形成に関しては短距離走ではなく長距離なので生産性も加味しつつ、チームの透明度を上げると行ったことが大切です
もっというと覚える順番も①>②>③の順番ですね
スタンスは癖がついちゃうと変えるのはなかなか難しいですよ
具体的なことと言えば、
・挨拶ができる
・掃除ができる
・時間を守る
こう言った当たり前の基準なのですが、ここの部分を後回ししちゃうとその後のチーム形成に関して正直ものがバカを見る状況のリスクが生まれやすくなります
個人として働く場合なら問題ないのですが
(それでもクリエイティブな部分では突っかかりますが)
チームとしての場合だと淡々と評価して判断するのが一手目としては必要です
私自身、飲食店経営者として10年以上やっておりますが、
就寝時間は21:00です笑
起きるのは4:00ですが
毎回この話をするたびに驚かれたり、
もしくは「この人、人生に楽しみあるの?」的なイメージで見られたり笑
外に視察がてら出かける時や臨店の時は、
もちろん夜中までありますが基本的に朝方人間で
それが性分に合っているんですよね
日課としては朝日報を見てから1日が始まるといった感じです
何か気になることがあれば返信をしてといった感じ
昔は週に2回ほどやっていたのですが、それらもどんどん減らして今はこの形です
最近はその返信業務も任せられるようになってきたのでどんどんシステムに注力が出来ています
基本的に店舗のミーティングも月に1回のみだし
それも基本はオンラインでやっており、臨店にする機会も減ってきています
よく
「社内での人間関係が希薄にならないですか?」
「それでどうやって店を回しているんですか?」
「問題って起きないんですか?」
と言ったことを聞かれるのですが、絶好調ですよ笑
去年から私自身が東京に来ており、
離れている体制がメインではありますが
過去最高売上・利益を更新していますし
もちろんスタッフには感謝しております
稲作の考えを仕組みづくりに取り入れています
まずは土作り、次に種を植え、水やり草抜きをし、収穫
このサイクルです
①ルールや仕組みと言った良い土壌があるか
②人という種
③良いよと誉めたり、ダメなところは正しく注意して
④収穫をしましょうよ
教育のサイクルの落とし込むとこういうことです
あくまで種(人)にばかり求めすぎず、まずは土壌作りが重要ってことです
つまりルールや仕組みが重要ってことです
その点にかけては長けている自信があります
なんせ朝から何年も取り掛かっていますから笑
かと言って丸投げにしすぎても良くなく、あくまで
・承認を事前にしている
・スタッフには「共有」をし、「納得」してもらい「行動」してもらう
・指示は口頭ではなく、文字やイメージを共有
・議事録をつけ、必ず振り返りから行う
といった具体定なエッセンス(飲食っぽくいうと秘伝のタレ)があるのですが笑
それぞれボリュームが多いテーマなのでまた書き記します
全然違う話ですが、
GW中業者さんとニュートンのホームページリニューアルの打ち合わせを
毎日朝・夕みっちりやってアップデートしましたがこれは良い!
改めて自社のサービスをマジマジと見たのですが、これ凄いですね笑
それも近々アップされます(本当は本日予定)
業務の効率化
前回書いたのですが、業務の効率化の狙いってまずは失点を防ぐことだと思います
スポーツで例えるなら
「5対4で今までは勝っているのを5対3にしたいよね」
そんな感じだと思います
得失点差が1だったのを2にしたいよねってこと
会社経営でいうところの利益が得失点差に当てはまります
スコアが1点あたり100万だとしたら
100万の利益を200万にしたいよねってこと
(変な賭博の話ではありませんよ、あくまでイメージ笑)
効率化の狙いとしてはそんな感じだと思うのですが、
重要なのは入り口よりも出口であります
うまく施策が当たった時に、利益が増えた時に、
どうするかってことを考えておく必要があります
あくまで効率化というのは手段であって目的ではありません
例えば
・従業員に還元してさらに頑張ってもらう
・経営者が堂々と頂く(これももちろんあり)
・とにかく会社を筋肉質体制にしておきたい
・(コロナで)会社の傷んだ財務を立て直す
・お客様に還元し、さらに得点を増やす
(これは単なる6対3ではなく、少しややこしい)
他にもありますが、ざくっと上記のようなものに還元が多いと思います
これらが目的としてその後に、どう正のスパイライルが出来上がるか
とても重要な経営判断として必要になります
失点を増やすことはなんとなく重要だと感じている場合も多いと思いますが、
セオリーとして
「バケツで水を汲む前に、バケツの穴を埋める」
このことを理解しておくと納得度が増すと思います
目的としては得失点さを増やしたい(もちろんプラスで)
そのためには得点を増やすのではなく、失点を減らすこと
物事には人やお金といったリソースが限られています
どこに集中すべきかの決断の時に間違ってしまうと手痛い失敗をしたくありません
策がない状況の中選択を迫られている状況の場合
「とにかく得点を増やしたい」と焦る気持ちもあるのですが、
一旦バケツの穴を埋めることに集中して良いでしょう
かといってやりすぎも良くないのでほどほど感が重要ではありますが
経費削減だけしておけば良いというのではなく順番が大事ってことですね
効率化に関してのまず第一歩は可視化だと思っています
とにかくアウトプットをすること
これに尽きます
でないと、集まりが変な方向に行きがちになりやすいので
+議事録をつける
+議事録を必ず振り返る
こういった当たり前の建付が必要になってきます
急がば回れってことですね
また追々、アウトプットの具体例等を示していければと思います